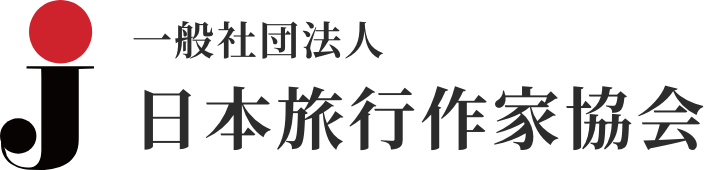香高英明/文・写真
サラエボ、モスタル(ボスニア・ヘルツェゴビナ)
2025年6月8日(日)
ある男の旅の視座・ボスニアヘルツェゴビナ編
2025年極暑の中で記す
その男は6月5日、イスタンブールへ向かう機内で、13時間近くをウトウトする時間と映画を見ることを繰り返しながら過ごしていた。様々な思いが脳裏を掠めるが、「旅の視座」という言葉が、脳裏にくっきりと浮かび出てきた。「視座」とは、物事を認識する立場を表し、「視座」が動けば物事を見る範囲にも影響し、その「視野」も変わる。「もっとも注意を注ぐポイント」を指す「視点」もある。その男は今回の旅を「どこから、どのようなものを見るか」を考え続けていた。そして、最後にはなぜか「旅奉行」と呼ばれていた。

その男は6月15日夜、イスタンブールから羽田空港に降り立った。機内ではほとんど眠れず、かなり疲れ果てていたため、タクシーに乗った。自宅では荷物の粗片づけを終えて、眠りについたことを覚えている。翌日以降はカイロプラテックなどで身体を整え、『バルカン半島4か国帰国記』の書き出しに入ろうとしていた。
だが、その男は「喉の痛みと咳、怒涛のように繰り返す鼻水、そして襲うってくる睡魔との闘い」に明け暮れていた。発熱はなく、1週間経っても症状は収まらず、医者に行っても風邪薬を処方されるだけで、2度目の診察でコロナと判断された。夜中にたっぷりの汗をかき、着替えるが効果なし。症状は3週間以上続き、その男は苦しんでいた。
その男は文月、愛逢月(めであいづき)と呼ばれる7月半ば、やっと『大いなる眠り』から目覚めたように感じた。『大いなる眠り』は私立探偵フィリップ・マーロウが登場するレイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説だが、「大いなる」でなく「長い寝込み」からやっと解放されたように感じた。
その男が2013年から3年間生活していたサラエボ、謂わば「里帰りの気分」になっており、12年後の変わり方は想像できない。その男の旅人生は、ほとんどが「個人旅」で、2000年頃から「生活する旅」が加わった。今回、バルカン半島4カ国を「観光する団体旅」によって何が観えたのか、まだ考え込んでいる。
サラエボで会いたかった人
2025年6月7日、朝8時にセルビアのベオグラードを出発した専用バスは、国境を越えてボスニア・ヘルツェゴビナに入るが、それぞれ検問所でパスポート提示、スタンプを押された。道は平原の4車線から2車線に狭まり、その道を上り下りし、山間を縫うように走る。ベオグラードからサラエボまでは約4時間程度だが、ヴィシュグラードでドリナ川に架かる世界遺産の「ソコルル・メフメト・パシャ橋」を観光したので、夕方遅くにサラエボに着いた。その男には、山国で、森の緑の中を澄んだ川が流れるこの国の様は、まさに渓谷美と思えた。
バルカン半島の中央に位置するボスニア・ヘルツェゴビナ、首都サラエボは山に囲まれた方円系の盆地に広がる。15世紀にオスマン帝国の支配下となり、トルコ風の建築物が多く建てられ、オーストリア=ハンガリー帝国の統治後は西洋風の建物が建てられ、東洋と西洋が混ざり合う独特な景観を生み出してきた。そのためか、イスラム教、正教、カソリック、ユダヤ教など様々な宗教と文化が共存している。

首都サラエボの街はディナール・アルプスに取り囲まれたサラエボ渓谷の中にあり、ミリャツカ川周辺に広がっている。専用バスは夕方遅く、黄色い色の壁を残したホリデイインホテルに着いた。
1992年、ボスニア・ヘルツェゴビナ分割交渉をきっかけに、クロアチア人勢力とボシュニャク人勢力との間で武力衝突が勃発、いわゆるサラエボ紛争が約3年間続いた。各国のジャーナリストは銃弾が飛び交う中、ホリデイインホテルを拠点に取材を続けていた。そして、その男は2013年から3年間、このホテルやスナイパー通りを見つめながら生活していた。
この日、ロビーで当地在住の日本人女性・宮野谷希さんが迎えてくれた。その男の「家のカミサマ」は2013年秋にボスニア大使館に文化広報担当としてこの地に赴任、その手始めにアメリカ大使館次席夫人(日本人)と日本語講座を始めた。最初は理解者がいたサラエボ大学農獣医学部で始め、2017年哲学部に移設されることになった。
彼女は2016年秋にマルセイユへの異動が決まったが、後任の日本人講師選びに難航していた。当時ベオグラードにいた宮野谷希さんにやっと決まったが、この講座を育ててくれたのが彼女だった。お互いの赴任の時期がズレていたので、会えずにいた。その男は7日夜の日本旅行作家協会の会食に招待、翌日は一部メンバーとランチを共にし、改めて感謝の意を伝えた。今彼女とともに活動するジェキチ美穂さんとは今回会えなかった。


3年生活した場をたどる、坂道から街中へ
その男は昔を懐かしむ訳ではないが、初めて本格的な海外生活をした街を再訪したいと思っていた。2013年から3年間、サラエボで主夫生活を始めた。60歳の定年を迎え、長年の放送局暮らしに飽き、お偉いさんのおもりに疲れ果てていた。また、60代で何が出来るか、チャレンジをしてみたい気分もあった。

6月8日、サラエボの旧自宅再訪のため、ホテルを出て街中のBBIセンタービルまで向かうが、街中の風景に懐かしさを感じる。その向かい側の公園を通り抜け、自宅に向かう坂道は数百メートルに及ぶ。古い邸宅風のEU大使館、フランス大使館、サラエボ紛争で銃弾を浴びたアパートを見ながら坂を上ると、コンビニ風の小さな商店に達する。
さらに細い路地裏を数十メートル上ると元自宅があった。ユダヤ人所有だった旧宅は取り壊され、EU大使公邸として建て替えられていた。向かいにあった建築中のアパートメントは、金策が付けば工事を再開するのを繰り返しているようで、10年経っても未だ完成していなかった。
その男は旧自宅跡を確認後、今度は街中に出る道を下りる。数十段の階段道もあり、途中に牛肉のカルパッチョの美味しかった店「ザチン」も残っている。当時、日曜は町はずれの大型スーパーに買い出しに出かけたが、平日は新鮮な食材を求め、坂道を上り下りする。果物、野菜、肉、ワインなどを背中のリュックに詰めて、一歩ずつゆっくりと。疲れたら途中のカフェで1杯100円ぐらいのエスプレッソを飲み、雪道ならさらにゆっくり歩く。その男は体力勝負に挑んでいたようだが、今思えばさらなる体力作りに役立った。
坂道階段を下りるとまず、ファーマーズマーケットの「マルカレ市場」がある。そして、隣の小さな魚屋でアドリア海産のアサリを仕入れる。スズキなどの魚もあったが、当時は鮮度を判断できなかった。その後は「屋内肉市場」で鶏肉や牛肉を買う。牛肉のヒレが1本6000円ぐらいで買えた。
ただ、ない時もあり、いつ入荷するかと尋ねると「tomorrow」という答えが返ってくる。翌々日行っても「tomorrow」、だから毎日通うことになる。イスラム系の多いこの街で豚肉を扱っているのは肉市場では1店だけ、これで基本的な食材がそろうが、BBIセンター地下の大きなスーパーで食材を探し、地下ではクリーニング店とも顔なじみになっていた。

中国人か日本人か?
その男が8日午前、旧自宅付近を彷徨している時、日本旅行作家協会のメンバーは「トンネル博物館」を見学したようだが、残念ながら白いお墓が立ち並ぶ競技場跡までは行かなかったようだ。
サラエボの五輪会場の多くは絶え間ない爆撃などで破壊された。紛争が終わってから20年以上経った今でも、貧しい国ゆえか、多くのオリンピック会場は放置されたままになっている。メインスタジアムには戦争犠牲者のお墓が立ち並び、フィギュアスケートが行われたゼトラホールは見本市会場などに利用されている。その男は、できたらこれらを見て欲しかったと思いやる。1984年の冬季五輪には、あの橋本聖子がスケート選手で出場していた。
それから10年も経たないうちに、サラエボはボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の中心地になった。疲弊したこの街に現れたのは中国人たちで、食料や物不足の中であこぎな商売を行い、サラエボ市内から追い出された。その男の2013年から3年間の滞在生活で、まず聞かれるのは「中国人か日本人か?」だった。日本人と言うと「おまえは友達だ」と、その男はどこでも歓迎された。だが、市内に中華料理店はなかった。


その男は路上に佇みながら考え込む。サラエボの街中には三つの宗教、イスラム教、正教、カソリックの教会が共存し、モスク、カソリック教会、東方正教会、ユダヤ教会は時間をずらして礼拝の鐘を鳴らす。人それぞれの見方や考え方があるが、「自分のやり方、考え方のこだわり」を取り除こうと思い、一歩立ち止まって「共存することの意味」を考え、歩むようになった。
その男はなぜかイスラム教圏の国々に縁がある。通い主夫していたマレーシアのペナンはヒンズー教、イスラム教、道教が共存。3か月住んだセネガルのダカールもイスラム教圏、そしてマルセイユにも地中海を渡ってきたイスラム文化が生きていた。
10年経ったサラエボ、変化するものより、変わらぬものが多い街だった。我が身は変わりたくもあり、変わりたくない気持ちも残る。70歳を越えて少しだけ「今生の別れ」を意識するようになったが、「これでお仕舞い」にはなかなかできない自分がいる。この世を垣間見て、決して深刻にならず、大仰な言葉は使わず、人生の深淵を覗き込むように言葉を吐露し、誰かに淡々と伝えることができたらと願う。
ボスニア料理と変わらぬ街中の光景
ボスニア・ヘルツェゴビナという国は2つの構成体で成り立つ。1つはクロアチア、イスラム系の「ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦」、もう1つはセルビア系の「スルプスカ共和国」。サラエボ空港近くには見えない国境線があり、サラエボ市内ではなかなか食べられないがスルプスカでは丸焼きバーベキューの豚肉が食べられた。
その男は今回の旅で、ボスニア料理が薄味になり、美味しくなったと感じた。実は生活していた時にはハーブと塩味の強いボスニア料理が苦手だった。そのため、肉のスライサーを購入、生ハムだけでなく、牛肉のカルパッチョ(生の牛肉が食べられた)、豚しゃぶなどを食べていた。このスライサーはマルセイユでも大活躍だった。一方手に入らぬ中華調味料、和食材と調味料は年2回の肝臓がん検査の日本帰国時に購入、その男の2つのスーツケースは、食材と旅猫GRISの餌と砂で占められた。
ボスニアの屋台料理の王様は「チェヴァピ」である。、パプリカ、トマト、ボスニアキャベツに、子羊、牛肉で作られた小さなひき肉のグリルソーセージにお米を詰めた煮込み料理だ。みじん切りの玉ねぎ、サワークリーム、赤唐辛子のソースが添えられる。バルカン半島独特の風味が豊かで、スモーキーな味わいが楽しめると言うが、その男の口には合わなかった。


「ラキヤ」はバルカン半島の伝統的なアルコール飲料で、食前酒、食後酒として楽しむ。このフルーツブランデーは通常プラムから作られるが、ブドウ、アプリコット、梨、リンゴなどのバリエーションもある。今回の旅の途中で、その男が「ラキヤを探している」と言ったら、専用バスの運転手が自分用のボトルからペットボトルに入れてプレゼントしてくれた。
その男は旅行ガイドブックの「2024年世界の都市」ランキングにおいて、サラエボは43位にランクインしたことを知った。ドゥブロヴニクは59位、リュブリャナは84位、ベオグラードは113位、ザグレブは135位だった。
その男は会社員を引退してから、趣味に、交流に、勉強と主体的に追求してきた。海外生活で、与えられたことに生きがいを見出そうとしていた。それが、主夫としての海外滞在経験だった。人生は頑張り続ける永遠のゲーム、どれほど頑張って輝いたとて、年を重ねれば、どんな人の元にも必ず訪れるものがある。
モスタルに向けて出発!?
6月8日午後、サラエボからモスタルに向かう時間が来た。バスはラテン橋のあるバシュチャルシヤ地区はずれにおり、ランチを終えたその男は宮野谷希さんと別れ、ミリヤッカ川沿いに10分ほどかけて歩いた。
出発時間は14時、だが1名だけ集合場所に来ない。どうやら場所と時間を記したスケジュール表を持たずに歩きまくっていたらしい。タクシーにも乗ったようだが、言葉が通じないと怒っていた。バスの中から2~3名が捜索に出るというが、危険な街中で何かが起きる方をその男は心配した。故に添乗員から見える範囲まで捜索という指示を出した。1時間近く待ち、やっと現れた。そしてやっと出発。
ボスニアはほぼ三角形をしている。国境のうち北側と南西側でクロアチア、東側でセルビア、モンテネグロと接する。クロアチアのダルマチア地方に挟まれたネウムでわずかにアドリア海に面する。ネウムでは小さな生牡蠣が食べられる。昔は国境越えを2回したが、今は高速道路橋が架けられたようだ。


サラエボから西南方向に山間の道をくねくね走るが、この道はまだ大型バスがすれ違える幅がある。石灰岩の岩肌と低木の緑、透明な川が見渡せる絶景の中を走っていると、羊を丸焼きにするレストランがあった、そこで休憩タイム、まだ羊を食べる時間ではなかった。その後約2時間以上走り、その男には見慣れたモスタルのブドウ畑が見えてきた。
モスタル(Mostar)はボスニアの人気観光地で、歴史的経済的にも非常に重要な地となっている。モスタルはボスニアの南西部、クロアチアから見るとスプリトの南東にあり、ドゥブロヴニクからは約3時間かかる。街の真ん中には南北にネレトヴァ川が流れている。クロアチア人とボシュニャク人の多数はネレトヴァ川を挟んで東西に別々に生活している。
中世まではキリスト教地域だったが、15世紀にオスマン帝国の支配下に入り、イスラム教地域となる。オスマン帝国衰退後は主にキリスト教とイスラム教が共生する町となり、それらの文化が建築などにも表れる。だが、ボスニア紛争で多くの教会やモスク、町の象徴でもあった橋「スタリ・モスト Stari Most」も破壊されてしまう
モスタルからクロアチア国境近くまで
6月8日夕方遅く、専用バスはやっとビジネス地区にある新しいホテルシティ モスタルに到着。部屋に確かバスタブがあったような気がするが、疲れもあり記憶が乏しい。
9日午前はモスタル観光、まずは世界遺産の「スタリ・モストStari Most(=古い橋)」。全長30m、水面からの高さは最大24mのアーチ橋はテネリヤと呼ばれる地元の石で造られているが、年寄りのその男にはとにかく歩きにくい。モスタルの昼間は観光客が多いので街歩きは早朝か夜にすること、ライトアップされた旧市街の夜の景色で滞在型の旅をするのが良いかもしれないと、その男は思った。
スタリ・モストの両側に広がるのが「モスタル旧市街の古橋地区」。歴史的な背景を残しつつ、レストランやカフェ、お土産屋さんなどが数多くある。その男は以前来た時にあったワイン屋をさがしたが、見つからなかった。「コスキ・メフメット・パシナ・モスク」はスタリ・モストの北東側、ミナレット(塔)のあるモスクで、階段で上がることができ、スタリ・モストと旧市街の眺めは絶景と言われている。だが、その男は相変わらず、寺院は眺めるだけだった。

サラエボからクロアチア国境、アドリア海が見えるまでは大きな山々を越えなければならない。その男はサラエボ在住時に季節ごとに山越えをしたが、その山々を越えた時に見える、石灰岩の岩肌広がる大平原の景色は忘れられない。モスタル、リブノ、コニーツの町を通る3つのルートがあるが、特に冬に一番北側を通るときに見られる景色は壮大なものだった。今回は一番南側のモスタル経由で、クロアチアのスプリト、トロギールに向かう。
9日昼前、モスタルを出てクロアチア国境に向かうバスに揺られながら、その男は様々なことに思いを馳せていた。妄想の中で、市井の社会には大きな川が流れていると思った。遠くに「赤い橋」が見えるが、それは渡ってはいけない河。人は目に見えぬ人間の、社会の規範に縛られるが、押しのけて歩み続けねばならぬと考えていた。
モスタルについては、JTWO(一般社団法人日本旅行作家協会)のウェブサイトの世界遺産の項に記している。以下に改めて記す。
モスタル旧市街の古い橋の地区
モスタルはボスニア・ヘルツェゴビナの5番目に大きな都市で、首都サラエボの南西120㎞の街、車で約3時間、長距離バスが毎日10往復程度運行されている。また、アドリア海のクロアチアの街ドゥブロヴニクからも約3時間、その他のクロアチア各都市とも結ばれている。
モスタルの由来はMost(橋)で、「橋の守り神」の意味を持つ。橋は人間ばかりでなく、神々や魔物も通る。サラエボには第1次世界大戦のきっかけになった血なまぐさいラテン橋があり、1993年の内戦時には「スタリ・モスト(古い橋)」も民族間の争いに巻き込まれた。2005年には世界遺産に登録された。

石灰岩の白さと緑豊かな渓谷美を持つ街モスタル、地中海性気候だが冬は寒く、夏は暑い。秋から冬にかけては雨が多く雪は少ない。市内を流れるネレトヴァ川に架かるアーチ状の石の橋「スタリ・モスト」は16世紀、オスマン帝国によって建造され、この街の象徴的存在になっており、ヘルツェゴビナ地方の観光名所として賑わっている。
欧州とは思えないような東洋的な雰囲気が漂うこの町は、歴史的、地理的背景からイスラム教徒とキリスト教徒が共存してきた。1993年のボスニア内戦時は、クロアチア系住民、イスラム系住民、セルビア系住民の激しい戦闘でこの橋は破壊された。その後ユネスコなどの協力で2004年に復元され、世界遺産として登録された。橋の近くには「93年を忘れるな」と刻まれた石が安置されている。
ネレトヴァ川、そこに架かるスタリ・モストは、今やイスラムとカソリック、正教、そして民族を繋ぐ橋になっている。スタリ・モストでは、街の猛者たちが川面から20m以上ある橋上から華麗な飛び込みを披露し、その完成度を競う伝統競技「ブリッジバンジージャンプ」も再開され、再び平和の象徴になりつつある。

スタリ・モストを中心としたエキゾチックな雰囲気が漂う石畳の旧市街、初期キリスト教のクリムバシリカ、オスマン時代のハンマーム(公共浴場)、時計塔、シナゴーグとユダヤ教徒の共同墓地など多くの教会、モスク類、修道院がある。
また、ネレトヴァ川河口寄りに向かうと、ブドウ畑などが広がっており、最近モスタル産ワインが注目されている。旧ユーゴは隠れたワイン王国で、アドリア海に程近いヘルツェゴビナ地方のものが有名である。