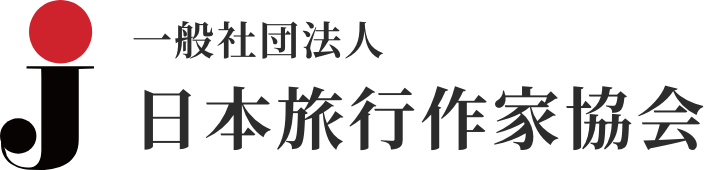川﨑洋子/文・写真
セルビア(ノヴィ・サド、ベオグラード)
2025年6月6日(金)
香りの記憶
香りは、特定の記憶を呼び起こすことがある。
「プルースト効果※」と呼ばれるこの現象を今回のバルカンツアーになぞらえると、リンデン※の花の香りは、ツアー初日の地、セルビアの記憶を彩ることになるのかもしれない。
※プルースト効果 特定の香りをかいだときに、その香りと結びついた過去の記憶や感情が呼び起こされる現象のこと。例えばバニラの甘い香りをかぐと子供のころにアイスクリームを食べた夏の日を思い出すといった現象。マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』の中で、主人公がマドレーヌを紅茶に浸した際に幼少時代の記憶を思い出す場面が由来となっている。
※リンデン 別名セイヨウシナノキ。ヨーロッパ原産のシナノキ科の落葉高木。ハート形の葉を茂らせ、花色は薄黄色で甘い芳香がある。花と苞葉をハーブティーとして利用すると甘く穏やかな香りと味わいで、心を落ち着かせる効果があるといわれ、蜂蜜の原料としても使われている。ヨーロッパでは郷愁を掻き立てるロマンチックな木で、ドイツの首都ベルリンの大通りであるウンター・デン・リンデンの両側に街路樹として植えられているのがよく知られている。
その甘く優しい香りは、ペトロヴァラディン要塞の急坂に一服の涼を、壮大な国際河川を望むカレメクダン要塞に伸びやかな風をもたらした。一方、ユーゴ解体後のセルビア経済復興の出遅れ感や公的部門の不安定感は短い滞在中にも散見され、かつての首都への事前の期待値からするとやるせないものがある。リンデンの花の香りに包まれた景色は、「国破れて山河あり」の一節を想起させる景色でもあったのだ。

以下、民族や宗教の交差路ゆえの陰翳に満ちたセルビアの訪問先、ノヴィ・サドとベオグラードを振り返ってみたい。
国境線の入植地(ノヴィ・サド)
セルビア第二の都市ノヴィ・サドは「セルビアのアテネ」とも称され、かつて帝国の交差点であった歴史がこの都市の特色を形成していると言える。また、ノヴィ・サドの都市名は、セルビア語で「新しい入植地」の意味である。
旅行記の筆を進める前に、ここで少し、この街の特徴を決定づけた歴史に触れておきたい。17世紀末の大トルコ戦争※を経てオスマン帝国との間に新たに設けられた軍事緩衝地帯を防衛するため、ハプスブルク帝国はペトロヴァラディンのような戦略的要塞を築き、多様な民族的背景を持つ臣民を国境防衛兵として入植させる政策を採った。彼らは永続的な兵役と帝国への忠誠を誓う見返りに、土地の割り当て・農奴制からの解放・信教の自由や税制上の優遇などが与えられ、これが当地における文化的多様性に繋がっている。しかし同時に、ハプスブルク帝国は、カトリックが優勢なドナウ川右岸のペトロヴァラディン要塞に正教徒であるセルビア人が居住することを禁じたため、彼らはドナウ川左岸に新たな集落を建設せざるを得ない状況に追い込まれた。この施策が当時独自の国家を持たなかったセルビア民族の文化的・政治的首都としての発展を促したのである。
※大トルコ戦争 17世紀末、オスマン帝国とハプスブルク帝国を中心とするヨーロッパキリスト教国の連合「神聖同盟」との間で、ハンガリー、トランシルヴァニアを巡って起こった戦争。欧州史における一大転換点となった。
短い滞在時間ではあったが、実際に歩いてみると、ノヴィ・サドの歴史的背景を所々で感じることができた。ペトロヴァラディン要塞は、大トルコ戦争の最中にオーストリア軍がオスマン帝国から奪還した後、既存の要塞を完全に取り壊したうえで当時の最新技術を結集して建設された88年間の大事業の成果物である。急坂の岩盤を登って要塞上部に入ると、稜堡(りょうほ)とみられる構造物跡やカラフルな漆喰の外観が特徴的なバロック建築の建物を見ることができた。軍事拠点としての役割を終えた現在の要塞上部には、博物館や芸術アカデミーなどの文化・教育機関が置かれている。なお、要塞最大のランドマークは、長針と短針が逆になった時計塔である。この一見分かりにくい設計は、ドナウ川を航行する船乗りや遠く離れた場所で持ち場につく衛兵たちが一目で「時」を判別できるようにするためのものらしい。



ペトロヴァラディン要塞からドナウ川左岸を見ると、ノヴィ・サドの中心部と思しき場所に、象徴的な二つの宗教建築が見えた。一つはセルビアの民族的・宗教的アイデンティティの象徴でもあるセルビア正教会。もう一つは、聖母マリア教会。対岸に渡り、近くで見上げてみると、高さ72メートルを超える尖塔は、カトリックを国教とするオーストリア=ハンガリー帝国の権威と影響力を視覚的に示す強力なシンボルのようでもある。


白い町の傷跡(ベオグラード)
昼食後、一行はバスでセルビアの首都ベオグラードに向かった。ベオグラードという都市名は、セルビア語の「ベオ (beo)=白い」と「グラード (grad)=町、城塞」を組み合わせた言葉である。この名前が定着した有力な説としては、高台にそびえ立つ要塞の城壁に当地で採れる白い石灰岩が用いられている事、あるいは、川を行きかう船や対岸から見える要塞が太陽の光を受けて白く輝いて見えたことなどに由来するとされている。
ここで再び、旅行記の筆をいったん止め、ベオグラードの地理的条件が当地の歴史にどのように影響を与えたのかを、軽くさらっておきたい。ベオグラードはパンノニア平原の中にあり、その中心部のカレメグダン要塞が建つ高台は、サヴァ川とドナウ川というヨーロッパの二大河川が合流する地点を見下ろす石灰岩の尾根となっている。つまり、ベオグラードは、広大なパンノニア平原とバルカン半島を結ぶ自然の十字路であり、水路と陸路が交差する交通の要衝なのだ。そして、その戦略的価値の高さゆえ、ベオグラードは常に大国の利害が衝突する「せめぎ合い」の歴史を刻んだのである。
このような大国の衝突と支配者の度重なる入れ替わり、それにより醸成されたナショナリズム。これらの痕跡を景勝地に垣間見るのもまた、観光のテーマであろう。ベオグラードで訪れたのは聖サヴァ大聖堂とカレメグダン要塞である。前述のテーマに沿ってこの2か所を形容するならば、前者は「信仰と民族意識を象徴する場所」、後者は「戦いと国家の歴史を象徴する場所」と言えるかもしれない。
聖サヴァ大聖堂は、聖サヴァの聖遺物が焼き払われたとされる場所に建てられている。聖サヴァは、中世セルビア王国の王子として生まれながら修道士となり、セルビア正教会を独立させた人物である。16世紀末、オスマン帝国の支配下でセルビア人たちが起こした反乱に対し、オスマン帝国の司令官シナン・パシャは反乱への報復とセルビア人の精神的支柱を破壊する目的で聖サヴァの聖遺物を焼き払った。しかし、この出来事は結果的には、その場所をセルビア人の民族的抵抗の象徴へと変えた。つまり、聖遺物が焼かれたまさにその場所に聖サヴァ大聖堂を建設するという計画は、支配の歴史に対するセルビア人の信仰と民族意識の「勝利宣言」とも言える。

一方、大聖堂の建設は、建造開始から90年経った今もなお進行中である。その背景には、第二次世界大戦による中断、宗教に否定的な立場をとる社会主義政権下での建設再開の遅れ、国家の財政難といった、セルビアの近現代史の困難が密接に連動しているのだ。しかしながら、その建設の道のりの苦難もまた、セルビア国民にとって、この場所をより一層特別なものにしているのかもしれない。工事遅延の最大の理由の一つである聖堂内部のモザイク画は非常に壮大かつ絢爛豪華である。訪れた日は幸運なことに特別な儀式があるとのことで、聖サヴァの聖遺物が運び込まれ、信者が長蛇の列を成して祈りを捧げていた。その姿は敬虔そのもので、観光客がいたずらに写真撮影するのははばかられたが、セルビア国民にとって宗教が日常生活に密接したものであることが窺われた。

この日最後の訪問地は、カレメグダン要塞である。地政学的重要性ゆえに、この場所は中世を通じて絶えず争奪の的となったが、その歴史を最も特徴的に形成したのは、東と西のキリスト教世界の対立、そしてキリスト教世界とオスマン帝国との間の文明的衝突であろう。今は市民の憩いの場である公園を抜け、要塞の西端まで行くと、サヴァ川とドナウ川が合流し彼方に平原を見渡す壮大な景色が広がっている。想像力をかき立てる、かなりのフォトスポットだ。しかし、その一角にある勝利の像にも目を向けたい。この男性裸体像は、当初はバルカン戦争でのオスマン帝国に対する勝利と解放を記念するものとして、市内の別の場所への設置が構想されていた。しかし、公の場での裸体表現に対する抵抗は強く、論争の結果、要塞の最も高い稜線上に移設されることになったという。像は右手に剣、左手に鳩を持ち、その視線はサヴァ川とドナウ川を越え、かつての敵国であったオーストリア・ハンガリー帝国の領土が広がっていたパンノニア平原の彼方に向いている。あくまで論争の結果の移設ではあるが、これにより、期せずして像の持つ意味にオスマン帝国に対する勝利だけでなく、第一次世界大戦におけるオーストリア・ハンガリー帝国に対する勝利の記念も加わったと言えよう。

1か所、どうしても違和感がぬぐえない場所があった。いや、厳密には「歴史的に理解できなくもないが懸念が消えない」と言った方が正しい。軍事博物館である。この博物館は、セルビアのオスマン帝国からの完全な独立が国際的に承認された直後の布告によって設立されたそうだ。外部展示では、第一次・第二次世界大戦やユーゴスラビア紛争で使われた戦車、大砲、装甲車といった巨大な兵器群が陳列されていた。古代の城壁に囲まれた、20世紀の紛争を物語る兵器。大国の思惑に翻弄され、支配者が入れ替わるたびに破壊と再生を繰り返し、それでも抵抗の末独立を守り抜いたセルビアの矜持を示しているようでもある。一方それは、つい30年前のユーゴスラビア紛争やNATO空爆も想起させる。忘れまいとする姿勢は大切であるし、一国の主張は尊重すべきである。しかしながら、生々しい展示による強いナショナリズムの発露は、これによる経済・外交上の影響を考えると、いささかインパクトが強いとも感じたのである。

「破壊と再生」の行く先
カレメグダン公園は、リンデンの花の香りに包まれていた。
その花言葉は、「夫婦愛」「結婚」「平和」「救済」など、総じてポジティブなものである。しかし、その香りに彩られた街は、破壊と再生の傷跡を残しながら前に進んでいる。来年の万博に向けて、この国はどんな再生の歩を進めるのだろうか。わずか1日の滞在ながら数多くの「歴史の痕跡」を肌身で感じた一行は、次の目的地に向けて旅立っていった。