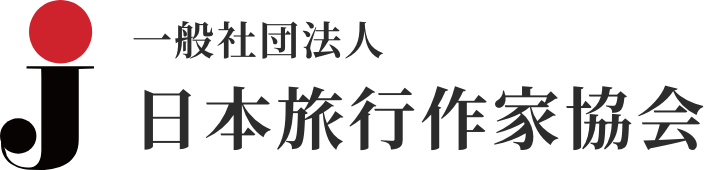市岡正朗/文・写真
トロギールへの旅(クロアチア)
2025年6月9日(月)
クロアチアの国の形
クロアチアという国の形を見てみれば、ずいぶん不思議な形をしている。
大きく「く」の字のような形で「く」の下のエリアは、もともとダルマチア地方と呼ばれ、アドリア海に沿って細長く南東にドブロブニクへと続く土地である。形の良い台形の国土が、太い矢尻のような形に大きく食い込まれたようになって「く」の字のような国境線になってしまっている。この大きく食い込んだ国がボスニア・ヘルツェゴビナである。
クロアチア人が古代のパンノニア地方(現在のハンガリー)から南下しクロアチア中部に移住したのが7世紀。ダルマチアとの統一を果たし、クロアチア王国を建国したのは925年頃である。

この中世クロアチア王国は、その後、ハンガリー王国、ハプスブルク帝国、オスマン帝国、ベネツィア共和国、フランス、イタリアなどなどに侵食され、支配され、分断され、国の形をなさない時代が続く。しかし、この中世クロアチア王国はクロアチア人のアイデンティティの拠り所となっているのだろう。ナチスドイツの傀儡国家として1941年に成立したクロアチア独立国は、この中世クロアチア王国に領土のおおよそが重なる。ただし、ダルマチア地方だけは除いて。この地はイタリア占領下にあった。
一方、ボスニア王国が成立したのは1377年。それがボスニア・ヘルツェゴビナのルーツである。しかしこの王国もオスマン帝国に征服され消滅する。しかしその記憶がボスニア・ヘルツェゴビナという国として復活させることになる。この混沌たる栄枯盛衰には、民族が、宗教が、そして文化が幾重にもクロスオーバーしている
ボスニアの地は失ったがダルマチア地方を取り戻して現在のクロアチア共和国が成立したのは、たった34年前の1991年のこと。国というものが、そして国境がこれほどまでにカオスそのもので、驚くほどの変貌を遂げてしまうのである。ダルマチア地方とはそんな時代の波に翻弄されながらも、クロアチアの中でも確固たる相貌をもって屹立するエリアである。
アドリア海の魚、アドリア海の塩
さて、このダルマチア地方の世界遺産トロギールを訪問したのは、バルカン旅行の5日目の夕刻であった。この日も、朝から雲ひとつない青空がひらけ、輝く陽がバスの車窓から見る緑の大地に降り注いでいた。バスで移動、そして移動、というのが今回のバルカンの旅。
この日は、ボスニア・ヘルツェゴビナのモスタルを見学し、国境を越えクロアチアへ入国。スプリトの街を観光し、トロギールに到着した。
紀元前3世紀のギリシャ植民都市のトラグリオに起源をもつトロギールは、クロアチア本土とチオヴィ島との間の小さな島である。


本土側のバスターミナルから歩いて橋を渡り、出島のように存在するトロギールという中世がそのまま封じ込められたかのような街に入る。細い路地が、迷路のように曲がり網の目のようだ。一見窮屈にも思える街路は石造りの壁に石畳の道。所々に点在するショップや木の緑などが彩りを添え、武骨でありながら典雅な中世の佇まいを見せている。ここではゆったりと流れる時が、その質を変えて、旅人たちを迎えているかのようだ。
ホテルはHeritage Hotel Tragosu(ヘリテージホテルトラゴス)。18世紀バロック建築の本格的ヘリテージホテルである。ヘリテージとは遺産を意味する。まさに名実とも世界遺産トロギールの中心に位置するホテルだ。ここに今日から2泊する。
その晩のディナーは、バルカンに来て初めての魚料理。最初のひと皿のフィッシュスープは、今までよほど魚の味に飢えていたのか格別の美味しさ。スズキ系の魚だろう、ほぐされた身がたっぷり入ったほんの少しとろみを感じさせるスープだ。まずひと口スープを味わう。香味野菜とともに頭も骨も丸ごと煮込んだ出汁の効いたスープは、旨味を舌に残したまま喉を滑り落ちていく。
次に身をと思いスプーンを近づける。よく見れば小粒の米が入っている。のちに添乗員の山田さんに聞けば、中世ベネツィア時代からのこの地方の食べ方で、スープは「身をしっかり食べる料理」とされて、米は食感を高め、また炭水化物源として入れるようになったという。米は14~15世紀、ベネツィア商人が交易で東方から持ち込み、このダルマチア地方で普及していったものだ。
メインは魚の塩焼き。これもこの地方の郷土料理スズキのグリルである。食べてみればその塩味にまろやかな甘味すら感じさせスズキの旨味を引き出している。このグリルは塩が決め手である。このまろやかで華やかで優雅ささえ感じさせるのはアドリア海の海塩。この風味、絶品の塩として世界に知られる同じ地中海のフルール・ド・セルに似ている。同じ地中海、製法に通底するものがあるのだろうか。考えてみればクロアチアの海塩も逸品として知られるものだった。

この晩のトロギール最初の美味しい邂逅は、これから出会うトロギールを予感させる上々のものだった
聖ロブロ大聖堂で想いを巡らせ
翌日、6月の10日、朝7時に起床。
朝食はビュッフェ形式。トマトなどの野菜とフルーツ。そしてチーズをチョイスしてオレンジジュース、と至ってシンプルなもの。もちろんランチとディナーに備えてのこと。
トロギールの散策観光は9時にスタート。
17世紀に建設された重厚なアーチ門の「北の城門」から始まった。次いで中世芸術の傑作とも呼ばれる聖ロブロ大聖堂、英語風に言えば、聖ローレンス大聖堂に向かう。ロブロ広場に面して建ち、隣には市庁舎、広場を挟んで向こうが時計台と旧裁判所に使われた建物。旧市街の中心だが、実際は島の東寄りにある。
この大聖堂は殉教者ロブロに捧げるものとして、13世紀に建築が始まったが、完成したのが17世紀とあって4世紀もの建築期間を経たことから、ロマネスク様式、ゴシック様式、ルネッサンス様式が混在するトロギールの歴史を象徴する建物となっている。

見どころはまず入り口のロマネスク様式の門。この門は13世紀のダルマチア出身の彫刻家ラドヴァンによって制作されたもの。門の入り口にライオンに乗るアダム(右)とイブ(左)の像。中央の天蓋にはイエスの生誕、その上のアーチにイエスの生涯が丁寧に彫られていて、クロアチアのロマネスク芸術の傑作とされている。しかし、なるほどと感心はしてみるがヨーロッパ中世の芸術や美術、そして建築には門外漢の私にはその価値を本当のところ理解できたかははなはだ疑問である。
ライオンはなぜかユーモラスだし、ライオンに乗るアダムとイブの何とも大きなイチジクの葉やイブの見事な垂れ乳に眼が行ってしまう。ギリシャ・ローマの彫刻と比べてもいかにも素朴で愛らしい。イエスの生誕も生涯も確かに物語として丁寧に彫られてはいるが、残念ながらこれらを相対評価するすべを私は持たない。ライオンは確かベネツィアのシンボルだが、このトロギールがベネツィアの支配下となったのは、この門ができてから2世紀後のことだ。ここに何の因果があるのか、そしてないのか。何ひとつわからないままひとりの観光客としてガイドの声にうなづくばかり。

旅するということは、ただ見知らぬ土地に行き物見遊山するだけではなく、その国や地域の歴史や文化にとって、自分がいかに無知なただの異邦人であることを思い知ることにある、のかもしれない。

大聖堂の内部は、混雑はしているが意外と清冽な雰囲気の空間。天井はゴシック様式の象徴でもある交差ヴォールトと尖塔アーチ。そのアーチからキリストが描かれた2つの巨大な十字架が吊るされている。身廊の奥には15世紀に造られた4本の柱の上に八角形の天蓋が置かれた石造りのバロック式主祭壇。主祭壇の前に木彫聖歌隊席が配置されている。サイドの奥に美しい部屋が見える。初期ルネッサンスの傑作といわれる、トロギールの守護聖人イヴァン・ウルシーニの石棺を祀る聖イヴァン礼拝堂である。
イヴァン・ウルシーニは、12世紀にトロギールの初代司教となった人物で、棺は十二使徒の像に囲まれて鎮座している。天井にはなぜか聖人が上半身を逆さまにのぞかせて祈っている。初めて見る造形にちょっとどきっとする。
ところで西洋の建築物は神に近づこうとするのかのように上へ上へと天に向かって伸びようとする意志を持つ。ゴシック建築の代表であるノートルダム大聖堂を見ればひと目でそれを理解することができる。一方、日本の建築物の神髄は横への組み立てにある。桂離宮の構成美がそれを代表する。
西洋建築は、ロマネスクにしろ、ゴシックにしろ、ルネッサンスにしろ、どの様式も上への意志は変わらない。しかし、時代ごとにそれぞれの様式、つまりそのデザイン性をきっぱりと貫くというのも、本来西洋建築に特徴的である。
だとするならば、聖ロブロ大聖堂のように、同じフロアの空間にいくつもの様式が混在しているという建築物は確かに非常に珍しい存在なのだろう。これがこの聖ロブロ大聖堂の、そしてこのトロギールの文化の最大の特徴なのである。

大聖堂の身廊や側廊の床には、いくつもの棺が床と一体化するように埋め込まれている。大聖堂の身廊には床に聖人たちの大理石の墓碑が埋め込まれ、床そのものが墓地になり、礼拝参加者つまり信徒がその上を歩きながら礼拝に参加する構造になっている。もちろん観光客もその上を歩く。大聖堂という空間で、まさか聖人たちのお墓を靴で踏んづけて歩くとは思いもしなかった。
他にもうひとつ激しく心に迫るものがある。黒いキリストの磔像である。中世にこのトロギールは3回ペスト(黒死病)の大流行に見舞われている。この黒いキリスト像はペストに苦しめられ困難を極めた人々の祈りが込められたもので、コロナを経験した私たちにとって、祈ることしかすべのなかった当時の暗澹たる民衆の怨念を込めたこの黒い磔像に、激しく心を揺さぶられるのである

プロムナードへ、そしてランチへ

大聖堂前の広場も、1000年以上も続く歴史が凝縮されたところでもあるが、ここでもロマネスク、ゴシック、ルネッサンスが共存する。
我々一行はこの広場を抜け、旧市庁舎、聖セバスチャン教会、時計台そしてロッジャ(市民集会所)を巡り聖スコラ修道院の前を通り過ぎ、南門から海辺のプロムナードへ出た。目の前にアドリア海が夏の日のまぶしい光を波間にきらめかせながら、小さな波を揺らしている。南門につながる城壁の前には、テラスレストランが並び、その前にヤシの並木。
プロムナードの先端に向かえば、15世紀にベネツィア人によって増築されたカメルレンゴ要塞がある。クロアチアの中でも、ひときわ数奇な歴史を持つダルマチア地方。かつてよりアドリア海の航海上、交易上の要所として位置づけられていたが、1402年からのベネツィア占領下に至り、ますますその重要性が勝った。海からの防衛拠点として、またネイティブなトロギール住民から、占領者としてのベネツィア人を守る拠点として、もとからあった城壁の砦を増改築して造られたものだ。出島のようなトロギールを陸方面から守る対となる要塞として、聖マルコ砦が同じ頃ベネツィア人によって造られている。


さて、ランチは大聖堂近くの郷土料理レストラン「Calepotta bar&restaurant」の裏庭ガーデンテラスでいただく。夏の香りのギリシャサラダ、一匹丸ごとのタイとスズキの塩焼き、エビとイカのグリル、ムール貝など海鮮をたっぷり盛り合わせたシーフードプレートをシェアしていただく。ワインはもちろん白。いかにもパッケージ旅行でのランチという趣だが、古来トロギール建築の裏庭らしい風情が、なんとも心地良い。隣の石造りの家の2階窓からは、ロープで洗濯物が干されている。もう一方の側面の石壁の上からは、太い木のツルが垂れ下がり、その壁の向こうには花木が見事な真っ赤な花を咲かせている。島民たちの暮らしもここにはしっかり息づいている。
フリータイムはひとり街歩き
今回この旅行参加者の多くがオプショナルツアーのスピードボートでのアドリア海クルーズに出かけたが、私は街歩きと撮影を選択した。再び南門からプロムナードに出て、島の南東チオヴォ橋に向かう。
橋の真ん中に立ち下を見下ろせば、アドリア海の深いターコイズブルーが広がる。対岸を見れば、チオヴォ島が緩やかな弧を描いて東へ伸びている。その岬は、緑が稜線をふちどり、白壁に赤レンガ色の屋根を持つ建物たちが段をなして並び、岬の突端に行くほどにその数を減らしていく。岸辺にはヨットやボートがずらりと岬の突端まで連なっている。岬の先のアドリア海に遠く橋が見えている。

振り返って見れば、右手にトロギールの城壁が大きくそびえる。その手前にいくつものテントにプロムナード。そして半逆光の陽に輝くアドリア海がゆったりと広がる。岸壁にはメガヨットと小さなボートが互い違いに係留されている。
次に旧市街を散策。

昨夕の陰りのある路地とは大きく雰囲気を変え、主要な街路はバラエティ豊かなショップが連なり、多くの観光客に溢れている。少し奥に入れば写真に撮りたくなる路地へと続く。石の壁にツタが垂れ下がったり、木がこんもりと樹木が膨らみを描いて立っていたり、緑の枝が壁の向こうから覆いかぶさったり。ふと足を止めれば、可愛らしいお店のショーウィンドーに並ぶ雑貨や、洒落たレストランへ誘う小さな入り口、ホテルのサインが目に入る。趣のある中世からの石の階段が時折アクセントになっていたりする。大きな壺に赤や黄、ピンクの色とりどりの花が植えられ、そこかしこのコーナーを飾る。古い石の建物だけがあるのではない。緑と花と、観光地としての人の営みが溶け合い、路地は思いのほか豊かな変化を見せている。
行き交う人々も、またこの路地を生き生きと引き立てている。どこにカメラを向けてもインスタ映えするのだが、やはり撮り続けてみれば、路地そのものの風情を写すには、店が閉じ観光客が引いた後のほうが良い、と思ったのだ。
旅人にとって、こんなふうに路地を歩く気分は格別である。右に左に思いの向くまま歩くのが良い。旅は「街の風に吹かれるまま」が良いのだ。1時間も歩いただろうか。街の奥行きが、頭の中でくっきりと像を結ぶ。この街が自分のものとなったのである。旅に出れば、いつもひとりでこんなふうに街を歩いている。旅先を自分のものにするひとつの方法である。

再びプロムナードに向かう。
プロムナードに向けて、思い思いにテラス席をはみ出させるレストラン&カフェが城壁前に並ぶ。その前のプロムナードは、観光客たちの格好の散歩道となっている。
プロムナードのいちばん奥、カメルレンゴ要塞寄りにあるレストランの50席もありそうなテラス席のいちばん前の席、つまりアドリア海に近い席を取り、オレンジ色のスパークリングカクテル、アペロールスピリッツを頼む。

正面に広がるのは、ボートがひっきりなしに行き交うアドリア海。その向こうに白壁、ピーチ色の壁、あるいはベージュ色の壁に、オレンジ色を溶かしたような煉瓦色の屋根が織りなす建物のチオヴォ島が遠望できる。夏の光を跳ね返す白壁たちと煉瓦色の屋根のコントラストが美しい。
旅の途中で、自分だけに確保された時間。
煌めくアドリア海を眺めながらのひと時は、特に何もする必要もなく、広い青い空の下、明るいまぶしい光の粒子が降り注ぐアドリア海と建物と行き交う人々を眺めるばかりの贅沢な時間だ。アペロールスピリッツのほのかな苦みと甘みが、時の流れの中の一瞬の清涼剤となる。おもむろに浅い岸壁に近づいてみた。小さなボートの下でたぷりたぷりと波の音がした。
至福のディナーはロゼとともに
さて、今宵のディナーは、3人の同行者とともに、旧市街のレストランでと決まった。
店先の大きなディスプレイ台の上に氷が敷き詰められ、その上に、大小の魚やロブスターが並べられていたレストラン「Kamerleng」である

この店先で、このディスプレイされた魚たちの中から、このお店の貫禄あるギャルソンと丁々発止の相談と交渉。同行者に英語ペラペラの女史がいたことも心強かった。まずはロブスター、ついでカサゴ、馬面のマトウダイをチョイス。やっぱりここは炭火焼でしょ、という感じでオーダー。
陽気なウェイターがロブスターを両手で広げ、私たちの写真撮影のために戯けてみせる。
レストランに併設されたテラスの6人用テーブルを4人で占領して大盛り上がりの中で宴が始まった。
前菜は、トロギールの名物、タコのサラダ。
新鮮なタコを柔らかく茹で、ぶつ切りにして、オリーブオイル、塩、胡椒、レモンにミニトマト、オリーブの実に緑の野菜と和えただけのシンプルなものだが、口に入れば、タコは柔らかいが確かな弾力とほのかな甘み、それを爽やかな野菜とオリーブオイルが包みこみ、レモンの酸味も効いて心地良い一品である。
ワインは白。品種はポシップ。

やや辛口でフローラルで華やかな香り、ミネラル感というかアドリア海の塩味を感じさせるかのような爽やかな後味。
広く切り取られたテラスの上の空はまだまだ明るい。
ロブスターが大皿に乗って、「どうだい、凄くないかい?」とでも言いながら運ばれてきた。
一同、歓声。
ギャルソンが大きなフォークとナイフを器用に操って見事に切り分け、めいめいの皿に取り分ける。ぷりっぷりの身をひと口噛めば、海の養分たっぷりいただきました、とでも言いたげな紛れもないロブスターの旨味と、海風のような爽やかな塩味が口いっぱいに広がる。
これぞ至福の時。

次に出てきたカサゴもマトウダイもギャルソンの手で上手に切り分けられる。4人はただ、その手さばきに感嘆の声をあげながら、香り立つその身の美味しさを想像する。
カサゴは、そのしっかりした弾力、濃い旨味が特長。骨から皮から出るコクが、その旨味を倍加させている。これは、アドリア海の濃厚な旨味の代表か。
マトウダイはきめ細やかな食感、癖のない甘みすら感じさせる風味が特長。カサゴとは一線を引くエレガントな旨味だ。これは、アドリア海の清冽な旨味の代表か。
合わせるワインは、SIKULIというブランドのロゼワイン。このレストラン近くの家族経営のブティックワイナリーで造られたワインで、ロゼなればこその現代的な夏の晩餐にぴったりの、ライトで爽やかな風味が際立つ絶品である。
炭火焼きの魚とともにワインを口に含めば、魚の旨味を宥めながら心地良い旨味を舌に残す。食の間にワインを飲めば、前の魚が残した旨味や雑味を残す舌をさっぱりと洗い流し、ロゼの極上の風味の余韻を漂わせる。
ギャルソンがロゼを手に、
「このワインを造るエリアはギリシャ・ローマ時代からワインを造っている」と自慢する。
後から調べてみると、その通りで紀元前2世紀にギリシャ人が入植しワイン造りを始めた。
その入植した古代集落を「Sikuli」という。なるほど、現在のワイナリーもその名に由来していたのだ。

また、このワインの品種は、Teran(テラン)という。アドリア海を囲むカルスト土壌の鉄分を多く含む土地と相性が良く、古代ローマ時代からダルマチア地方で栽培されていたという記録があり、豊かなタンニン、強い酸味、濃いルビー色で知られたワイン品種である。この品種をモダンな醸造で、まろやかでありながら酸味がさわやかなロゼとして仕立てたのが、このSIKULIのロゼワインだった。
古代ギリシャ人・ローマ人の残したワイン文化の直系の末裔の1本というロゼワインを、私たちは心ゆくまで堪能したのである。
ところで、ダルマチア地方に古くから語り継がれていることわざに「魚は3度泳ぐ」というものがある。
1度目は、海の中で泳ぐ
2度目は、オリーブオイルの中で泳ぐ
3度目は、ワインとともに泳ぐ
というのがその意である。
1、はいうまでもない。
3、もアドリア海の魚とともに味わう白ワインとロゼワインの見事さを知れば充分理解できる。
さて、問題は2である。
昨日のスズキのグリルと今日の炭火焼きもその旨さの秘密に大きくオリーブオイルが働いている、ということに食べてみれば気がつくはずだ。
下ごしらえにオリーブオイルを塗り、乾燥を防ぎ、焦げつきを防ぎ、しっとりとした食感と香ばしさを高める。加えて、魚のはらわたにオリーブオイルを垂らし、深いコクを出している。さらに焼き上がりにもオリーブオイルをかけ食感を高め、艶やかなコーティングを作り出す…。
多分、そんなふうにオリーブオイルは使われている。カサゴのなるほどのコクも、マトウダイの繊細な風味もオリーブオイルがアドリア海の海塩とともに決め手なのだ
海鮮とワインを心ゆくまで楽しんだディナー。4人が4人とも旨さに触発されはぜるように歓談し、愉悦に浸り、そして時に我を忘れたのだった。
これは紛れもないトロギールの”美食”との出会いだった。
ふと見上げればテラスの上の広く切り取られた空は、深くて濃い、夜の藍色に染まり始めていた。そろそろお開きの時間が来たのだ。
夜の散策、歴史を刻む石畳
ホテルに戻り、シャワーを浴び夜の路地へと繰り出してみた。

昼間見た観光客がぐっと少なくなり、翳った路地にはしっとりとした風情が漂っている。街灯やホテルやレストランの看板の明かりを、路面は静かに映し込んで鈍く光っている。時折、レストランからは、語らいの声も漏れ聞こえてきたりする。
昼と夜、2つの刻を歩いてみて、この街には陰影のある深い表情があることに気がついた。
1242年、モンゴルに追われたハンガリー王ベラ4世は、この小島に逃れて命をつないだ。その後3世紀以上にわたりこの地を支配したベネツィア共和国は、城壁と要塞を築きアドリアの防波堤としてこの地を守り抜いた。ハプスブルクの旗が翻り、ナポレオンの軍靴が迫り、二度の大戦の嵐がアドリア海を、バルカンを蹂躙しても、トロギールは石の迷宮としてその存在感は変わらなかった。いくつもの帝国に欲され、幾度となく逃亡者を匿い、そしてパルチザンの拠点ともなった。トロギールこそはアドリア海のそんな歴史の交差するところ。黒光りする石畳の路地が、そのすべてを刻み込みながら、いまも旅人に語りかけてくるかのようだ。
今回の旅で2泊したのは、トロギールだけだった。だからこそ、この街の昼と夜、表と裏、その陰影の深さを垣間見ることができたのだ。トロギールは、いまなお私に強い印象を残し、忘れがたい街となっている。