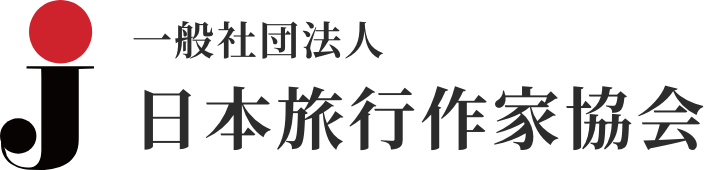芦原伸/文・写真
ティラナ&クルヤ(アルバニア)
バルカン紛争のこと
バルカン半島の旅は印象深い。
思い出すのはユーゴスラビア時代のベオグラード。サヴァ川に浮かぶ水上レストランでのことだ。現地ガイドのジュリア嬢とランチを食べた。ジュリアは小麦色の肌、黒髪の美女、取材最終日で感謝を込めてご馳走したのだ。愛敬のあるシェフに歓待され、地元農家の自家製ワインを飲み、サヴァ川で獲れたカワカマスに舌鼓をうち、ゆったりとした午後を過ごしていた。1990年、東欧革命のただ中のことで、ベルリンの壁は崩壊し、ルーマニアでは革命が起きていた。しかし、ここベオグラードはチトーが指導した西側寄りの緩やかな社会主義が浸透し、街には自由な気分が横溢していた。その時、ジュリアは、
「私たちの国には五つの顔(民族)があるのよ。それを一つの顔(国)になれ、と言われても、やはり難しいわね」
と、美しい横顔を見せて何気なく放った言葉が忘れられない。
その後、1年も経たないうちに血みどろの紛争がはじまり、半島は真っ赤な血に染まり、民族はそれぞれ独立し、七つの共和国が誕生した経緯はご存知の通りである。バルカンは“ヨーロッパの火薬庫”とまで呼ばれた。
さて、アルバニアである。アルバニアはユーゴスラビアには与しなかった。ユーゴとはスラブ語で「南」の意味、ユーゴスラビアは「南スラブ人」の連合国であった。アルバニア人の先祖は古代民族のイリュリア人といわれ、印欧語族でスラブ語系とは血筋が違うのである。しかし、この国もコソボをめぐりセルビアと血で血を洗う戦闘を交えた。コソボはもともとセルビアの自治州であり、セルビア正教会の拠点であり、セルビア人の聖都というべき存在だった。しかし住民のほとんどはアルバニア人である。現代のウクライナ戦争にも似ているが、ロシア正教の発祥地、聖都キーウをプーチンが強権を発して奪い返そうとする構図にも似ている。結果的にコソボは独立宣言したが、セルビアはじめ幾多の国々は今も承認には至っていない。
6月27日(木)
午前中はティラナ市内
午前中は、雨上がりのティラナ市内を散策。市内中心部に位置する国立歴史博物館は、改修工事のため閉館中で中に入れなかったが、スカンデルベグの騎馬像や18世紀のモスク、ジャーミア・エトヘム・ベウト、国立考古学博物館などを見学した。革命公園にトーチカ(塹壕)が展示されていたのが印象的であった。






郷愁感漂うオールドバザール
そして午後、私たちは首都ティラナから36km、バスで1時間ほどのクルヤに来ている。クルヤ城址で知られる観光地である。ちょうどお昼時で展望の良いレストランで昼食となった。料理メニューはイタリア系、トルコ系とバラエティに富み、ワインコレクションも豊富だ。“ヨーロッパの最貧民国”などと誰が言ったのだろうか、と首を傾げる。窓から眺める丘陵にはイチジク、オリーブ畑が広がり、白壁とオレンジ屋根の2、3階建ての瀟洒な民家が点在する。まるで南仏のリゾート地のようである。店は混んでいたが、客は白人系は少なく近隣諸国からの観光客のようだ。“火薬庫”と呼ばれた時代はとうの昔で、今はエレガントな雰囲気の中、グルメとワインを楽しんでいる。外で一服すると、「中でも平気だよ」と客のオジサンがわざわざ助言に来てくれた。なんとも心優しい国なのである。

食後、クルヤ城へと向かった。
古い石畳の坂に沿って、「オールドバザール」と呼ばれる一角があった。みやげ物や絨毯を売っている。15世紀から続いているトルコ様式のバザール(市場)で、天井から空を覆うばかりに絨毯や婦人用のワンピース、テーブルクロスなどが垂れ下がっている。店頭にはトルコ石まがいのブローチやペンダント、木製の皿やスプーン、動物のフィギュアなどの雑貨が多く、なかにはなぜか日本刀などもあり、買い物慣れした日本人の購買意欲にはつながらないようだ(といいつつも格安のトルコ石のブローチを妻への言い訳のために購入したが…)。

アルバニアの英雄、スカンデルベグ
クルヤ城址に入った。大砲やら国旗(双頭の鷲)やら、ワケありの糸杉の巨樹などあるが、岩山をバックにした「見張り台」が唯一の歴史的遺物だろうか。もはや朽ちかけており、整備された城址の中でひときわ異彩を放っていた。
ここでの見ものは「スカンデルベグ博物館」だろう。スカンデルベグ(1403-1468)はアルバニアの英雄である。民族独立のためにオスマン帝国と戦い、3度にわたり敵軍を撃退したという。
博物館に入ると、山羊の頭の兜を被り、鎧をつけ、ガウンをまとい、右手に剣をもつスカンデルベグの像が私たちを迎えた。顎鬚を蓄え、彫りの深い、精悍な顔立ちは威厳がある。武将というよりも知将を感じさせる風貌である。
スカンデルベクは幼い頃人質としてイスタンブールに送られ、イスラム教徒となり、成人してベネチアやセルビアと戦い功を立てた。時の皇帝ムハンマド二世がその功績を称え、かの大王の名にちなみ「イスカンデル(英名アレキサンダー、ベグは尊称)」との名を与えた。
1443年、アルバニア人の対トルコ蜂起の報に接し、民族の自由のために戦うことを決意。キリスト教に改宗し、首長たちを結集させてオスマン帝国と戦った。しかし、1466年、ムハンマド二世は自ら大軍を率い、スカンデルベグを攻撃。劣勢のスカンデルベグは支援を求めローマを訪れたが、その帰途、ベネチア領アレッシオで客死したといわれる。アルバニアは彼の死後オスマン帝国の支配下に入り、歴史上沈黙することになる。


1982年開館のスカンデルベグ博物館の外観と館内展示の一部
つくられた英雄だったか
アルバニアではどこへ行ってもスカンデルベグの立像、胸像に出会うことだろう。国の中興の祖のような存在だが、しかし、私はどうも素直に伝説を受け入れることはできないでいた。果たして中世のその時代、アルバニア人は国として独立の覇気、民族意識を持っていただろうか?
私の意地悪い想像だが、スカンデルベグを英雄として祭り上げたもとはヨーロッパ、とりわけローマ教皇だったのではなかったか。カソリック諸国にとって、オスマン帝国は最大の敵であり、かの十字軍の宿敵である。しかもたかだかアジアの片隅から風のごとく移動してきた遊牧民が作った国なのだ。それが強大な帝国としてのさばり、イスラム世界の盟主となっている。それに反旗を翻し、オスマン帝国を叩いたスカンデルベグをヒーローとして讃えたい、というのがローマ教皇の本音だろう。
その後独立したアルバニアは社会主義国となる。社会主義国には国家の英雄が必要である。そこでスカデルベグは国の英雄として浮上したのではなかったか? 歴史はいつも後から作られるものである

オスマン帝国の不思議とは?
オスマン帝国はヨーロッパ諸国からすれば「悪者」であり、衰退した20世紀初頭には“瀕死のヨーロッパの病人”とまで酷評された。しかし、それはあくまで西洋史観であることを忘れないでおきたい。アジア側からすれば600年継続した帝国はほかにあっただろうか? 中国の唐さえ300年に過ぎない。しかも、領土はアジア、アフリカ、ヨーロッパの三大陸にまたがる比類なき広大さである。
大帝国維持にはローマのように強権が必要とされるが、オスマン帝国はその逆で、彼らの支配は緩やかで、他民族、他宗教を受け入れ、女性や文化人にも活躍の場を与えた。今でいうならば「多様性重視国家」であった。たとえば、各支配地の領主の子らをイスタンブールへ来させて教育し、修養させ、成人したら領地へと帰してやり、その地を統治させたのである。スカンデルベグもそうした一人で、本来は北アルバニアの領主となって収まるはずだった。また宗教にも寛容で、イスラム教を強制せず、オスマンの軍隊にはキリスト教者もユダヤ教徒も共存していたのである。緩やかで多様性を尊ぶ姿勢だったからこそ600年もの間帝国を継続できた、といわれる。
アルバニアの街にはモスク、正教会、カトリック教会が共存している。夫がムスリムで、妻がカトリックという夫婦もいるときく。飲酒、喫煙も自由だ。オスマン時代、人々は至って平和に暮らし、トルコ文化になじんできただろうことは古い街の佇まいやキリスト教会の存続、郷土料理(ほとんどトルコ料理に近い)などから想像できる。
バルカン半島をめぐる旅は、その緩やかで多様性に富む人々の生き方、イスラム寺院やビザンツ正教会など多彩な宗教遺産が魅力なのかもしれない。